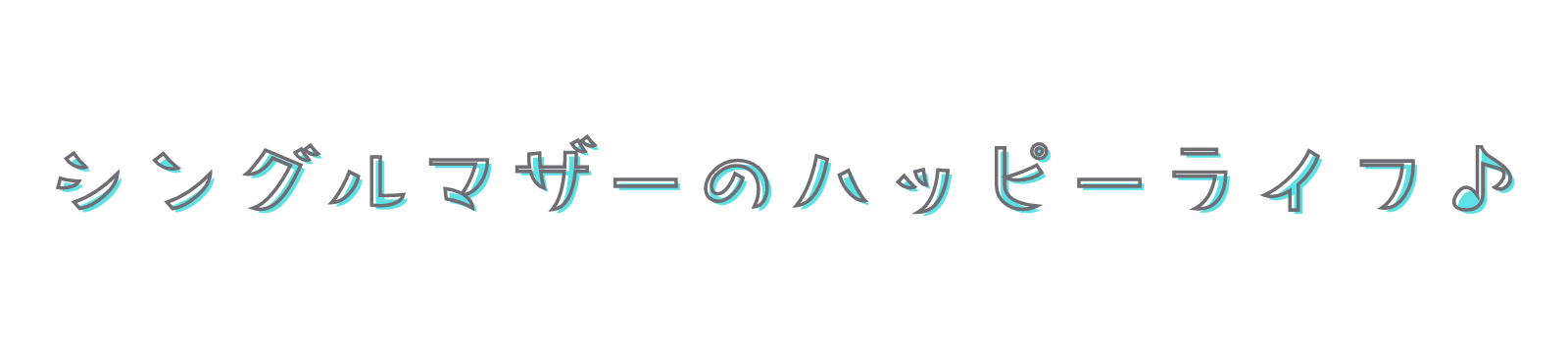未婚の母になりますが、子父に認知してもらわない選択をすることでどんなデメリットがあるの?
未婚で妊娠・出産する未婚の母の場合、上記のような疑問を抱えてしまう女性は多いのではないでしょうか。
未婚の母にとって、そして子どもにとっても父親に認知をしてもらうかどうかは今後の人生を左右する非常に重大なこと。

今回の記事では、未婚シングルマザーである筆者が未婚の母が子父に認知をしてもらうデメリットについて詳しくご説明していきます。
未婚の母から産まれた子どもの認知について

まず、未婚の母から産まれた子どもの認知についてをご説明していきましょう。
ご存じの方がほとんどかとは思いますが、未婚妊娠・出産だとしても、母親と子どもの間には認知する・しないの問題は生じません。
なぜなら、母から子どもが産まれてきたという揺るがない事実があるからです。
しかし未婚の男女の間に産まれた子どもは、父親が認知をしてくれなければ法律上親子関係が認められないのです。

法的に親子関係(父親であること)を認めてもらうためには、子どもの父親に必ず認知してもらう必要性があるのです。
未婚の母が認知に慎重になるべき理由
未婚の母が子どもの認知に慎重になるべき理由は、認知をしてもらうと子供の戸籍に子父の名前が載ってしまいます。
そして、認知は法律上取り消すことができません。
唯一の取り消せるケースは、認知した子どもが実の子でない場合のみとなります。
後程詳しくお伝えしますが、子父の立場によっては認知をしてもらわない方がいいケースも考えられます。

一方、子の父親に認知をしてもらうデメリットが特にない場合は、未婚の母であり認知もしてもらっている私の意見としては認知をしてもらった方がメリットが多くあると感じています。
一番のメリットは、子父に認知をしてもらうことで法的に父親の存在を明らかにし、養育費の請求や相続権を得ることができる点ではないでしょうか。
まだ未婚で子どもを産む決断が出来ていない方は、まず下記の記事から読んでみてください。

未婚の母が認知なしを選択するデメリット
未婚出産のシングルマザーが、子父に認知をしてもらわないことを選ぶデメリットは、主に下記の5つのことが挙げられます。
- 子父への未練が残る
- 過去に執着して前を向いて生きられない
- 養育費の請求ができない
- 父親の相続権が認められない
- 父親の存在を法的に証明できない

それぞれの事柄について、未婚シングルマザーである私の経験を踏まえてご説明していきます。
子父への未練が残る
未婚出産で認知をしてもらわないことを選択する場合、子父へ未練が残ってしまう可能性が高いです。
もちろん、選択的シングルマザーとして自らが未婚の母になる決意をしたのならば、子父への未練は特にないでしょう。
一方、子父に認知をしてほしいのに子父からは「認知はできない」と言われ、子父の言葉を鵜呑みにして自分自身の気持ちを押し殺してしまうと子父への未練が残りがち。

認知から逃げる子父を認知させるのは非常に難しいため、認知を望んでいるのならば弁護士さんにまず相談してみるのがいいでしょう。
過去に執着して前を向いて生きられない
本当は認知をしてほしいのに、なんらかの事情で子父に認知をしてもらわない選択を選ぶと、過去に執着して前を向いて生きられない可能性も大きくなります。

私の経験上、納得した上での結果なら受け入れて前を向けることが多いのですが、納得していないのに無理やりその結果を押し付けられても前を向けないことが多いです。
子父に認知をしてほしいのに認知をしてもらえない場合、毎日認知をしてもらえないことを悔やみ、子父への恨みでいっぱいの中生きなければいけない状態になる方も少なくありません。

過去を手放すには、あなたが納得できる方向に行動していくことが必要です。
養育費の請求ができない
子どもの認知をしてもらわない最大のデメリットは、養育費の請求ができないことでしょう。
ちなみに、養育費は原則子どもが20歳になるまで、又はお互いの合意があれば大学卒業まで貰うことが可能。
日本では養育費の未払いが多いという問題がありますが、そもそも家庭裁判を通して法的に効力のある方法で認知や養育費の請求をしていないケースも多いのではないでしょうか。

私は認知ありで養育費も毎月受け取っています。養育費があるから経済的にも精神的にも余裕が生まれるようになりました。
認知をしてもらっていない状態では、子と父親の親子関係が法的に認められないため、養育費を請求する権利が与えられないのです。
父親の相続権が認められない
認知をしてもらっていない状態では、子の父親が死亡した場合子供に相続権が発生しません。
相続権も養育費と同様、子どもに与えられた権利ではありますが、その権利を得るためには認知は絶対的に必要なものなのです。

子の父親に財産が全くない場合は認知してもらうメリットがないかもしれませんが、隠しているケースもあるのでなんともいえませんよね。
父親の存在を法的に証明できない
子どもの認知をしてもらっていないということは、法的に親子関係を証明できるものが一切ない状態になってしまいます。
例えば、子どもが大きくなってから父親の存在を説明しようとしても、戸籍などをみせて証明させることができません。

あなた自身は認知の必要性を感じていなくても、子どもにとっては重要なことであるケースも。将来のことも考えて認知をしてもらうかどうかを検討しましょう。
未婚の母が認知なしを選択するメリット
一方、未婚出産で認知をしてもらわないことでメリットがあるとするならば、下記のことが挙げられるでしょう。
- 時間やお金をかけなくて済む
- ストレスを抱えなくて済む
- 慰謝料請求されない可能性が高い
時間やお金をかけなくて済む
相手が認知から逃げている場合、話し合いがスムーズに進まず認知をしてもらうまでに時間がかかってしまったり、弁護士に依頼しなければいけないケースが多いでしょう。

1人で子育てをしながら認知の話し合いや、認知の手続きを進めるのは現実的にかなり厳しいです。
子父が認知から逃げている時点で、どうしようもない男性である可能性は非常に高いのではないでしょうか。
- 無職である
- 低収入なので養育費を期待できない
- トラブルメーカーである
- 常に女性問題で悩まされていた
などの場合は、認知なしを選択するメリットは大きいかもしれません。
ストレスを抱えなくて済む
認知から逃げている子父にそれほど未練がない場合は、認知をしてもらわない選択をした方が、ストレスを抱えなくて済むでしょう。
なぜなら、先ほどお伝えしたように認知をしてもらうには時間とお金(主に弁護士費用)がかかってしまうことがほとんど。
話し合いに応じてくれない相手ならば、ストレスを与えられる可能性が非常に高いです。

認知調停や養育費調停は、想像以上にストレスがかかりますので、認知を求めるメリットがない相手ならば向き合わないことの方がストレスがかからない場合もあるでしょう。
慰謝料請求されない可能性が高い
不倫をして子どもができた場合も、子の父親には認知をしてもらうことは可能です。
しかし、子父が既婚者である場合は、認知をしてもらうと子の父親の戸籍にあなたの子どもの名前が載ってしまいます。
子の父親の戸籍にあなたの子どもの名前が載るということは、奥さんは子父とあなたが不貞行為をしていた事実を知ることになるので慰謝料請求してくる可能性が非常に高いでしょう。

既婚者の結婚詐欺などの場合はまた話が変わってくるので、弁護士さんへ相談するのがいいでしょう。
このケースで認知をしてもらうと、遺産相続トラブルに巻き込まれる可能性もでてきます。
ですから、人によっては子父が既婚者である場合は認知なしを選択することで得られるメリットはあるといえるでしょう。
認知をしてもらえない子どもの気持ちは?
未婚妊娠・出産をしたのならば「父親に認知をしてもらえないなんて子どもがかわいそうだ」と思うこともあるでしょう。

私自身も、認知をしてもらえないということは子どもの存在をないものにされているようで非常に嫌でした。そういった気持ちもあり、子父には認知をしてもらいました。
戸籍は日常生活の中でほとんどみる機会はありませんが、子どもが結婚する際などには戸籍をみる機会があるでしょう。
ですから、子父に認知をしてもらっていないことを一生子どもに隠し通すことはできません。
残念ながら、認知をしてもらえなかった子どもの気持ちを実際にきいたことはありませんが、認知をしてもらっていないことで子どもの気持ちが複雑になってしまう可能性は高いように感じています。

私の考えではありますが「認知をしてもらっている=存在を認められている」と捉えることもできます。ですから、子どもの自己肯定感を高めるためにも認知はしてもらった方が子どもにとってもいいのではないかと考えております。
とはいえ、認知に関しては人それぞれの気持ち、価値観や状況がありますので一概にはいえません。

私の意見は、未婚出産を経験した1人のシングルマザーの意見としてきいていただければと思います。
まとめ

未婚出産で認知をしてもらわないデメリットやメリットをお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

人それぞれの考え方や生き方があるので、この記事を読んでご自身の意見がよりまとまることを願っております。
「無責任な父親とは関わりたくもない」と認知を拒む未婚シングルマザーさんもいらっしゃるかもしれませんが、それだけの理由で認知をしてもらわないのはデメリットも大きいです。

私の場合は認知をしてもらったことにより、毎月養育費を受け取れています。認知をしてもらったメリットは非常に大きいと感じています。